ただ今馬場研究室では、馬場先生、石原先生、内田研究員と学生の木根、高橋、石井、ゴンザレス、渡邊でドクターコースのゼミを進めています。今期からの試みとして、学生の中には仕事を持ちながら勉学に励まれている方がおられるので、スカイプなどを使って遠隔地からでも対話ができるような方法を取り入れながら行いました。
そこで今期の最終Dゼミが行われた後に、普段はカンボジアで活動されている高橋さんが広島に来られたこともありお酒を飲みながら議論を交わしました。懇親会では普段のゼミとは違う話もでき、皆さんの研究活動に取り残されないように、私自身の研究もどんどん深めていきたいと改めて思いました。
研究活動の中で、難しいと感じることは多々ありますが、一週間もしくは一ヵ月前から何かしら成長を感じるときがあります。こういった感覚を楽しみながら進めていきたいと思います。
渡邊耕二
2011年7月31日日曜日
2011年前期ドクターコースゼミ終了
ラベル: Daily story, 渡邊 耕二
2011年7月20日水曜日
全国数学教育学会から感じたこと
6月25、26日に広島大学で全国数学教育学会研究発表会が開催されました。
馬場研究室からは、石井さん、ゴンザレスさん、渡邊が発表いたしました。3人とも発表直前まで入念な準備をしておりました。日本の数学教育学の発表会で開発途上国の数学教育における研究の話をするわけなので、私たちのセッションではオーディエンスは決して多くはありませんが、活発な意見や日本の数学教育研究者から意見は、非常にシャープなものだと感じています。なぜならば、客観的な視点からの意見である場合が多いからです。
馬場研究室は、開発途上国の数学教育に関する研究に取り組む人が多いですが、その基盤となる理論や考え方は、日本のものを参考にする場合が多いです。なぜならば、わが国の教育協力への貢献を意識しているからです。二足のわらじを履くような研究スタイルですが、既存の学問に触れることは、何かの本質を追及する上でとても大切なことです。本質を見る視点や観点は人それぞれだと思います。しかしながら数学教育という以上は、数学の学問としての特性を無視することはできないでしょう。
私は、数学という学問の価値を非常に感じております。数学者は、数学には「美」があると言うことがあります。その美とは何でしょうか。おそらく学校で取り扱われる数学からその美を感じることはまずないでしょう。感じても「不思議だな~」というまでではないでしょうか。学校で扱う数学では感じることができないからといって、横に置いておいてよい感覚ではないと思います。数理的な構造の中にある「美」、これはシンメトリーな図形の美しさ、夜景や星空を見たときの感覚に近いものだと思います。数理的な構造を可視化したものがシンメトリーな図形や、一見ランダムに見える星空だと考えられるからです。では目に見えない数理的な「美」といえば、方程式の解やある関数の構造または数理的な事実の証明の中に現れてきます。
今統計学を勉強しておりますが、統計学でいう相関係数は、数学の線形代数の言葉で説明すれば、COSθでしかないのです。COSθといえば、高校数学で習う数学の関数ですが、相関係数というものに結びつきます。その証明は非常に簡単ですが、既習事項が別の概念に結びついてしまう。これは数学の威力そのものなのだなと感じます。またフェルマーの最終定理という350年間誰も証明できなかったものがあります。それは三平方の定理をa^2+b^2=c^2 を満たす自然数a,b,cは無限にありますが、途端に指数の2を3や4に変えた場合には、それを満たす自然数a,b,cは一つもないというものです。この小学生でも理解できそうな問題を証明するために、なんと350年の時間がかかりました。この定理は約20年ほど前に証明されましたが、最先端の数学が使われました。その証明の過程には、多くの日本人が貢献し、特に「全ての有理楕円曲線はモジュラーである」という谷山・志村が提示したいわゆる谷山・志村予想を解決することでなされました。そこには、一点の曇りもない途方もない理論が積み重なり、誰にでも理解できそうな単純な数理現象が証明されました。また別の問題で一見ランダムに何の規則性もなく現れると思われる「素数」の並びには、実は合理的で完璧な規則性を有するのでないかという予想があります。リーマン予想と呼ばれますが、現代物理学と結びつく非常にパワーを持つものだとされています。
このように数学には、問題そのものや問題の対象は、学校数学で触れるものであるが、壮大な歴史と未来への期待を秘めているものがあります。実用性が重視される現代の数学教育の中で、数学的な美的感覚を養うことは、一つの数学教育学の課題になるのではないだろうか。
数学なんてなぜ勉強するの?とよく生徒はいう。私はある意味では数学に触れる、学ぶことは、部活動と似ていると思います。例えば、野球部に所属しているからプロ野球選手になるわけではありません。しかしプロ野球選手にならないからといって、高校野球で燃え尽きるまで打ち込むことに意味がないとは思いません。体力がついて警察や自衛隊を目指す、チームワークが身について別の組織でやっていく、集中力が身について一流の科学者になるかもしれない。数学をすることもこれに近いものだと感じています。
数学そのものは教育的でない、という感じることもありますが、開発途上国で数学教育を論じる場合には、計算問題しか扱わないなど言われることがあります。確かにそれだけでは物足りない感じはしますが、計算が速く正確に行えること、さらに計算問題に打ち込んだ経験があること、これらそのものに教育的価値があると思います。日本とは異なり、計算問題、機械的な授業が多くみられる途上国では、その中から子どもたちが何を学んでいるかをプロ野球選手にならないけど野球部でとにかくやり遂げるといった観点から分析することが、数学教育開発の課題になり得るのではないかと考えています。
数学をする意味、途上国にみられる難しい計算や大半を占める機械的な授業から得られるものの本質を見極めたいと思います。
渡邊耕二
2011年7月1日金曜日
海外の算数教科書~アフリカの教科書事情とそれを取り巻く事情~
アフリカと言っても53か国あり、北はアラブ諸国から、南は温帯の国までその多様性はほかの大陸以上と言えるだろう。ここではザンビア、ガーナという地理的には離れているが、英国の植民地化を経験した国々を例として、描写していきたい。
アフリカと聞いて、まず何が思い浮かぶだろうか。飢餓、貧困、内戦、もしくはアウトドア派の人ならば、サバンナ、マサイ族、野生動物などであろうか。両者ともに、アフリカの一面を物語っていることは間違いない。ただし、都市にはやはりビルが立ち並び、数百万人の単位で住人が住む。もちろん多数は農村部で生活し、そのような中では電気水道などが来ていない村も存在する。
1960年がアフリカの年と呼ばれることをご存じだろうか。この年に多くのアフリカ諸国が独立したためであるが、それから数えれば来年がちょうど50歳である。人間の一生とは単純な比較はできないのかもしれないけれども、アフリカ諸国は半世紀の間に様々な経験を重ねてきた。
○教育事情:多数の問題を抱える
現在アフリカ諸国は、上に挙げたような困難を抱えている。また教育に限定しても、高い中途退学率などの量的問題に加えて、教室内で行われる教育の質的問題がある。もちろん後者の質を左右するのが、教員である。その他にも重要な問題として、教授言語(旧宗主国の言語)の影響は見逃せない。子どもたちにとって日常使う言語ではない英語、仏語、その他言語による学習は、ただでさえ難しい内容をより難しくする要素といえる。
○教員か教科書か?
このような問題が多様・多数存在する中で教育改善を行うために、教員の質を高めるのか良質の教材を配布するのかという議論を聞くことがある。もちろん両者は一体化して初めて意味を持つのであろう。しかし、アフリカの現状を見るとき、資金や人材が限られている中で、両者を一気に解決していくのは易しいことではない。その時にこのような提案が出てくるのは自然かもしれない。
教材配布の提案は大きくいえば、ティーチャー・プルーフ・カリキュラムの考え方に基づいている。それは教員の力量によらず、特定のカリキュラムや教材を使うことで、均一のそして良質の教育が行えるという発想である。プログラム学習はそこから来ている。ところが1973年OECD教育革新センターのセミナーで指摘されたとおり、世界的にはこのような考え方は古いものとなりつつある。
○教科書の量と質
アフリカの教育はこのような背景を持っている。その中で、教科書について語るとき、その量的側面と質的側面の両方から語られるべきであろう。前者は援助国・機関が配布を支援することによって、時には大量に印刷配布され、一時的に多く出回る。とは言え多くの場合には全ての生徒に教科書が行き渡ることはない。さらに、質的な側面がこれに絡んでくる。公的な機関が責任を持って良質のものを安価に作成し、全国に配布することが理想だろう。しかし、現状はそれとは反対の方向に進んでいる。「公的な機関が能率悪く粗悪品を作っている」という理由で、教科書産業に市場原理を取り入れ、改革(政策策定ザンビア1996年、ガーナ1998年であるが、実施は4から5年後)が進められてきた。結果は、教科書の質は上がったのかもしれないが、ザンビアでは教科書が一冊1000円前後もする結果となって、教室の中で教科書を有する子どもはほとんどいない。この動向には、多国籍教科書企業(マクミラン、オクスフォード大学出版など)がいるかも知れず、問題の解決は一筋縄ではいかない。
○教科書の内容
次に教科書の内容について幾つかの特徴を挙げたい。
*集合
現代化の影響の中で代表的なものが集合である。アフリカ諸国も1960・70年代に影響を受けた。国による差異はあるものの、いまだにその影響は残っている。ある意味では、各国が自主的な判断をしていると言えるかもしれない。ザンビアでは集合という言葉がそのまま使われている。ガーナではグループ分けを通して、数の抽象性を感じさせる方向性は理解できるが、色や形状が違うものを扱うために、かえって混乱を招く可能性も見える。
*スパイラル・メソッドと数の取り扱い
複数年に渡り繰り返して学習するスパイラル・メソッドが、教科書の大きな特徴である。極端な話、各学年に現れる単元名はほぼ同じで、内容が少しずつ難しくなっている。
例えば日本の場合は、三桁まで丁寧に扱い、その中で数の規則を意識させ、4年生の内に一気に兆の位まで学習する。それに対して、たとえばザンビアでは6年生まで、百の位(2年生)、千の位(3,4年生)、万の位(5年生)、百万の位(6年生)のように、非常に丁寧にゆっくりと進めて行く。
*量の取り扱い
線分図そして数直線は日本の算数教育にとって、離散量から連続量への展開を図る上で重要な役割を果たしている。それに対し、これらの国では乗除や分数などで補助的な役割を果たしたり、長さを示したりすることはあっても、一貫して取り扱われていない。
*図形の取り扱い
図形は内容量が少ない。さらに内容そのものも焦点がやや不明確である。特に、ザンビアではその傾向が強い。2年生で形を少し学ぶ他、面積は意識させるものの図形は出てこない、形の名称を覚えるだけになってしまっている部分もある。
*日常場面の取り扱い
良い点も取り上げたい。日常場面や応用がかなり意識されているように思える。ものの売買や測定などの日常的な場面を通して、数学を習得していく姿勢は注目に値するであろう。
○今後の展望
アフリカの教科書事情を見てきた。そこでは諸問題、その背景にある社会的条件や援助国・機関の影響などが分かった。それらを乗り越えていくために、単純に「教員か、教科書か」について議論するだけでは済まないだろう。教材・教科書作りを通して教員の力をつけて行くこと、教員の経験を生かして教科書をつくることのように、その両者の融合した解決が求められる。現実の子どもや教員・学校の実態が反映された教師による教師のための教科書開発が必要になる。そこでは、各文化・社会が持つ固有の民族数学の応用がますます注目されるべきだろう。
50歳を目前にアフリカ諸国が今後中進国の仲間入りを政策に掲げている。そのために、教育の充実は急務と言える。アフリカのスポーツ選手の躍動感のように、近い将来躍動感を持つアフリカ社会を見たいものである。
2011年6月23日木曜日
◇過去の記憶とスコール◇
以前フィリピンの離島に滞在していた時に使っていたノートから、
必要な情報を抜き出していたら、ある一節を見つけた。
「それにしても、日本での私たちの暮らしを振り返ると、豊かな暮らしを享受しているはずの私たちが、まだ起こるとも起こらないともわからない漠然とした将来の不幸に対する不安から、‘生’が実践されている今という時を、ほとんどその保障のためにあてがっていることに気づく。私はあの男の人のさわやかな表情をいつまでも心に留めておきたいものだと思った。」(インドの樹、ベンガルの大地より)
南の国の人特有の緩慢なうごきと、からっとした笑みを何ともなく見ていると、
かなり前にインドで描写された一節に、再び息が吹き込まれたように感じる。
何かとやることが多かった日本から抜け出し、
熱帯の湿気に包まれてスコールを眺めていると、同じ世界でも場所によって時間の
流れ方がずいぶん違うのだなあと思ったりする。
雨季の入り口にさしかかっているルソンより。
Taikai Takahashi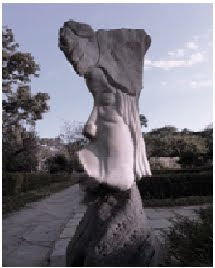
2011年6月14日火曜日
深い~い話

先日、なるほど・すごいな・やっぱりな、と思う話を飛行機の中のラジオでききました。
それは王貞治氏が、インタビューに答えている場面でした。王さんはイチローの凄さをを語っていました。
「彼はある意味僕と似ていて、どんな記録を打ち立てようとも達成感というものを感じないんですね。」
「僕はいつも子どもたちに野球がうまくなるにはどうすればいいか聞かれるのですが、いつも答えるのはとても単純なことなんです。毎日練習をし毎回努力すること、これが大事だとね。イチローも同じことをやってきたんだとね。子どもたちにとってあまりインパクトのある話ではないですが・・。」
これを聞いて思ったことは、凄い人だからこそ人の凄さがわかる、ということです。凄くない私などは、イチローはいつも冷静沈着、自分をコントロールできる人だなあ、くらいにしか感じていなかったけれども、王さんは違っていました。「達成感を感じない」なんて、なるほどな・すごいな、やっぱり王さんだな、とつくづく思いました。
On the airplane from Tokyo to Hiroshima yesterday, listening
to the radio, I heard the soft voice. That was Oh Sadaharu’s. He is the one of the famous baseball players in the world.
When I was a child, he used to be a hero that made a world record, 756 home runs. I clearly remember the scene he hit the home run, because it happened on the day of summer festival of my tiny village during summer holiday.
In the program on the radio, he answered the interview, “In a since Ichiro is similar to me because he has never felt a sense of accomplishment whatever he has made some records.”, and he continued “I always advised children that the most important thing to improve your skills was just practicing baseball every day and making an effort every time. Ichiro dose the same. The only thing he has done is practicing continuously and strictly. The advice I made does not give an impact to them but very important.”
To my impression, a great person knows what “a great” is. I thought Ichiro is a person who has a character of self-possessed and can put himself under the control. In a contrary, Mr. Oh Sadaharu focuses on a sense of accomplishment as a factor of Ichiro’s success. It is a deep insight that the person who did the same things could say.
ラベル: Daily story, 新井美津江
2011年6月2日木曜日
最近のデジカメ事情
最近のデジタルカメラの流行といえば・・・
裏面照射型CMOSセンサー!!
さて、この裏面照射型CMOSセンサーとはいったい何なのかを大雑把に説明します。
基本的にカメラのセンサーには大きく分けてCCDとCMOSという2種類のセンサーがあります。
少し前までのセンサーは大体がCCD。基本的にCCDの方がCMOSよりもきれいに撮れるってことでデジタルカメラは大体がCCDでした。
しかし、裏面照射型CMOSセンサー搭載モデルはCCD搭載モデルに比べて「高感度」、「ノイズが少ない」、「ダイナミックレンジが広い」等の特徴を持ち、「暗いところでもよく撮れるカメラ」として最近では定着しているのです。
さてその仕組みはといいますと、従来のCMOSセンサーはどうしても光を受ける面の上に配線がかぶさるような仕組みになっていて光を全部受け切れなかったのに対して、裏面照射型CMOSセンサーはこの配線と光を受ける面を逆にすることによって光をより受けることが出来るようになったのです。これが暗闇でも強い理由です。
どうしても暗い場所での撮影になってしまう学会発表・・・うまく撮影できなかったことは無いでしょうか?
そんな皆さん、ぜひこの裏面照射型CMOSデジカメをお試しください。
ラベル: Daily story, 須藤 絢
2011年5月11日水曜日
震災から2カ月
私たちの日本に深刻な影響をもたらした、3.11の未曾有の災害から2カ月が経つ。全世界、日本全国、広島大学内も含め、これほど復興支援のムーブメントが大きな波となって拡がることは、過去になかったのではないだろうか。それだけ、この復興と人々の精神的ダメージの回復には膨大な時間を要するだろうことが、その裏側にはある。
東北の知人や、現地に入った人の思いを聞くと、ある共通したことが含まれていることに気付いた。それは、これだけ甚大な被害を受け、身も心も大きな疲労に包まれているたくさんの人がいる中で、しかし、圧倒的大多数の人は、震災の前も後も変わらぬ生活を続けているという事実であり、被災した土地からそうでない土地へ移動したときに、その世界の違いに驚くというものだ。あるいは、被災地の中でも瓦礫のすぐそばには坦々とした人々の日常の営みがそこに在り、外から入った者はその光景の中にある、凄まじい現実と、人々の変わらぬ日常の営みという二つのもの混在に、ある種のギャプを感じる。でもそれは、被災地の人が、現実を受け入れ(そうではない人もいる)、力強く復興の根を大地に下ろし始めているサインなのかとも思う。
また、その世界の違いというものは、私たちが遠く離れた被災地が、今はどうなっているのかという想像力を働かせるときに、それを難しくしている要因であるようにも思う。実際に見えないもの、思いを想像することは簡単ではない。ましてや、あれから2カ月が経った。人々の関心は時間の経過に反比例していくものだ。この遠く離れた土地でできる数少ないことの一つは、思いを風化させないことだ。被災地への人々の関心を、細く長く繋げていくことなのだと思う。震災から2カ月という今日、ここに思いを投稿させて頂いたのも、自分を含めた人々の思いを風化させたくないという、一つの戒めであるかもしれない。
かつて集落のあった場所(相馬市)



